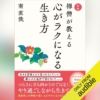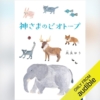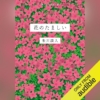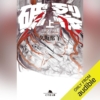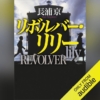直木賞候補&受賞の話題作!科学×地方物語10万年スケールで紡ぐ5つの短篇集『藍を継ぐ海』──徳島のウミガメ、北海道の隕石、山口の萩焼、長崎の被爆資料、奈良のニホンオオカミ…地球と命、伝統と未来を感じる感動長編
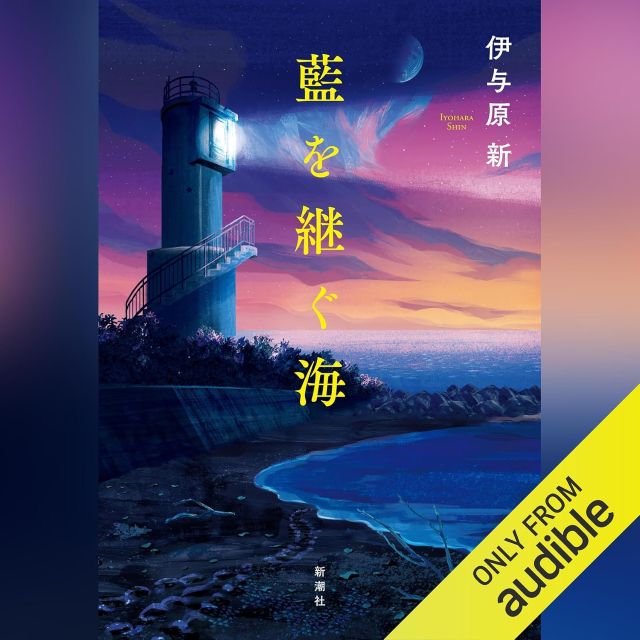
伊与原新(いよはら しん)さんの最新短篇集『藍を継ぐ海』は、第172回直木賞受賞作として、文学と科学を融合した新境地を開いた傑作です。舞台は徳島・北海道・山口・長崎・奈良と日本各地に広がり、全5篇を通じて“継承”というテーマが横糸として浮かび上がります。
① 表題作『藍を継ぐ海』(徳島県・阿須町)
徳島の小さな海辺の町で、中学生の沙月が祖父とともにウミガメの卵を孵化させようと奮闘します。夜中、卵をこっそり自宅に持ち帰り、やがて海へと旅立つまでの過程で、黒潮にのって大海を巡るウミガメの長い時間の流れと、沙月自身の成長とが重なって描かれます。
“すべては巡る”という佐和の言葉が象徴するように、人間も自然も大地も、壮大なサイクルの一部なのだと実感させられる、詩情豊かな一篇です。
② 『星隕つ駅逓』(北海道・遠軽町)
遠軽町の廃止間近な郵便局──“駅逓”。そこに落ちてきた隕石を巡る物語では、妊婦の妻・涼子が父を守るために隕石発見場所を偽るかどうか葛藤します。
宇宙からの贈り物と、過疎化する町の現実が交差し、人々の住む時間と地球の長い歴史とのズレに胸を打たれる描写は、まさに“体温のある科学”の魅力です 。
③ 『夢化けの島』(山口県・見島)
萩焼に使う伝説の土=“見島土”を探す地質学者・久保歩美と、元カメラマン・三浦光平の出会い。島の千二百万年前の火山成因と文化がリンクし、科学と芸術、個人と歴史が共鳴します。
作者の地球惑星科学者としての視線が、島の大地の形成と人々の営みに立体感を与え、読みごたえのある篇となっています。
④ 『祈りの破片』(長崎県・長与町)
被爆地にまつわる空き家で、溶けた瓦や岩石を山のように発見した公務員・小寺。これらは原爆投下後の歴史の“物理的記録”ともいえるもの。
混乱の象徴であるガラクタが、ときに“祈りの破片”に変わる瞬間を、小寺の成長の物語として描写した深みある内容です。
⑤ 『狼犬ダイアリー』(奈良県・東吉野村)
都会から移住したウェブデザイナー・まひろが、ニホンオオカミの“狼混”(オオカミ交じりの犬)と遭遇し、地域の子どもや自然とつながっていく話。
交流を通して内面が開き、“狼混”の存在が、人間の孤独も共有の一部なのだという視点を静かに照らします 。
≪作家・伊与原新の魅力≫
地球科学と文学を自在に行き来する背景からくる“科学的リアリティ”は、本作でも随所に光ります 。
研究者としての冷静な観察眼と、物語描写に込められた人間洞察の温かさ──このバランスこそが彼の筆致の基盤です。
また各地に根ざした背景設定の精緻さ──徳島の海岸、北海道の郵便局、火山島、長崎の空き家、吉野の山村──は、まるで舞台ドキュメントのように息づいています。
≪なぜ今、読むべきか≫
いまを生きる私たちにとって、「過去から未来への継承」は、緊急かつ普遍的なテーマです。地球規模の時間と私たちの日常が交わる瞬間を、五篇それぞれが丁寧に照らしてくれます。
直木賞選考でも、科学を題材にしつつ人間ドラマに昇華させた作品として高く評価されています 。
≪まとめ≫
『藍を継ぐ海』は、自然・科学・伝統・記憶・地域──これらを“継ぐ”ことの意味を、五つの物語を通じて静かに、でも深く問いかけてきます。
心揺さぶる感動と、新たな視座をくれる充実の272頁。直木賞作品の中でも、特に“時間”を体感できる一冊として、強くおすすめします。
ぜひ書店や図書館で手に取り、伊与原新さんが描く「人と地球の時間の物語」を味わってみてください。