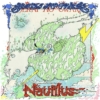華やかな編集部から絶望の底へ――息子の“事件”が暴く光と闇。追われる男が見つけた、新たな再生の光『夜がどれほど暗くても』一人生き残った被害者の娘・奈々美から襲われ、妻も家出してしまった。奈々美と触れ合ううちに、新たな光が見え始めるのだが…。

副編集長として輝かしいキャリアを築いていた志賀倫成(しが・みちなり)は、大手出版社の看板雑誌『週刊春潮』でスキャンダル記事を連発し、社内外から賞賛を一身に集めていた。世間を騒がせるスクープを手がけるほどに、「スキャンダルこそが会社を支えている」と確信し、編集者としての手応えと誇りを日々噛みしめていた。
しかし、その幸福はある朝、息子・健輔(けんすけ)が大学生の同級生をストーカー殺人した挙句、自ら命を絶ったという疑惑の報により、一瞬にして崩れ去る。取材の対象から一転、「事件を起こした家族」として凄まじいバッシングを浴び、倫成は社内の最下層──問題雑誌『春潮48』への左遷を言い渡される。かつては憧れの的だった同僚たちからは陰口を叩かれ、取材先には扉を閉ざされ、精神は擦り切れていく。
さらに、事件の被害者である女性の娘・奈々美(ななみ)から直接詰め寄られ、感情のはけ口にされる。怒号や罵声、突きつけられる「死んだ息子の父親」への憎悪。妻は心の均衡を保てず家を出て行き、倫成は人間関係すべてを失った孤独な戦場に立たされたような日々を送る。
だがある日、奈々美の視線の奥に、同じ喪失を抱えた弱さと痛みを見いだす。互いに“事件の当事者”としてしか向き合えなかった二人が、静かな対話を重ねるうちに、やがて小さな共感の芽が育っていく。問いかけるのは殺された彼女の母でも、責任を問うマスコミでもない、ただ「人としての優しさ」。奈々美の心と向き合う姿勢こそが、倫成にとって初めての「光の兆し」だった。
砕け散った日常の中で、倫成は再び「編集者として、人間として何ができるのか」を模索し始める。夜がどれほど暗くとも、そこに必ず朝は訪れる──。本作は、絶望の淵に立たされた男が、過去の過ちや痛みと向き合いながら再生へと歩み出すヒューマンドラマである。