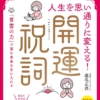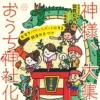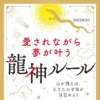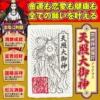古代神話が息づく日本列島を巡る――『古事記に秘められた聖地・神社の謎』は、八百万の神々が宿る神話の舞台を聖地考古学とフィールドワークで掘り下げ、創世神話から大和王権成立までの日本誕生の裏側を鮮やかに描き出す一冊。
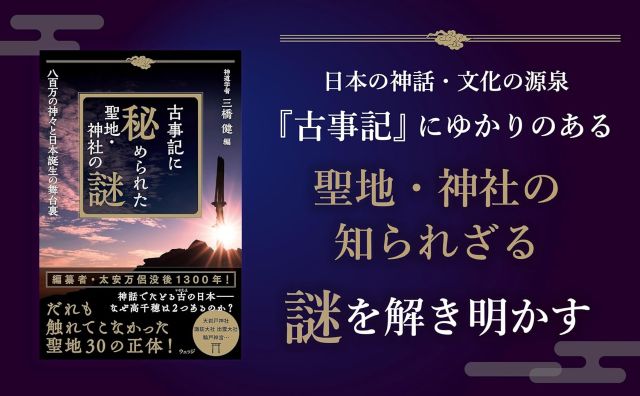
序章:神々の足跡をたどる旅
日本最古の歴史書『古事記』には、天地開闢(てんちかいびゃく)から大和政権成立までの神話が記され、八百万(やおよろず)の神々が登場します。本書はまず、オホナムチとスクナヒコナの国づくり神話、イザナギ・イザナミによる国生み・神産みの物語など、創世譚の聖地候補を概観。淡路島、出雲地方、壱岐・対馬の磐境(いわさか)など、神々が降臨したと伝わる主要地を地図と図版でビジュアルに紹介します。
第1章:国生み・神産みの舞台裏
イザナギ・イザナミと淡路島
イザナギとイザナミが天沼矛(あめのぬぼこ)を使って最初に生んだ「おのころ島」は、淡路島と比定されるケースが有力です。島中央の沼島や淡路市の伊弉諾神宮を訪ね、地形・伝承・祭祀痕跡を通じて「国生み神話」の実像に迫ります。
出雲の大国主とスクナヒコナ
オオクニヌシが因幡の白兎を癒したという稲佐浜や、スクナヒコナと共に国づくりを行った八束水臣津野命神社(やつかみずおみつのじんじゃ)を取材。2柱の神の役割分担や、交易・農耕が萌芽した痕跡から神話と現実の交錯を読み解きます。
第2章:皇祖神と王権の成立
天照大御神と伊勢神宮
皇室の御祖であるアマテラスが天岩戸に隠れた伝説は、三重県の伊勢神宮と深く結びつきます。内宮・外宮の起源伝承、遥拝所としての斎宮跡など、神宮の地政学的重要性を考察。
ニニギ降臨と高千穂
高千穂峰に降り立ったニニギノミコトの伝承を、宮崎県高千穂町でフィールドワーク。山岳祭祀と農耕文化の融合が、ヤマト王権へとつながる過程を掘り下げます。
第3章:地域神話と聖地の多様性
日本各地に点在する「小さな古事記聖地」を紹介。例えば、福岡県の宗像三女神を祀る宗像大社、群馬県のヤマトタケルゆかりの榛名神社、長野県の諏訪大社など。地元民俗や伝統行事を通して、古事記神話がいかに地域文化に息づいているかを浮き彫りにします。
第4章:聖地考古学と未来への視点
最新の発掘調査や空中レーザー計測(LiDAR)など考古学的手法を駆使し、古代祭祀跡や神殿の痕跡を再検証。デジタルマッピングで神域の広がりを可視化し、観光保全と地域振興を両立させる「神話ツーリズム」の可能性を提言します。
終章:八百万の神に抱かれて
古事記の神話は、単なる昔話ではなく、日本人の自然観・死生観・国家観を形づくった根幹です。本書を通じて読者は、古代の儀礼や信仰が息づく聖地を五感で体感しながら、八百万の神々とともに日本の原風景を旅する興奮を味わえます。
――神話と歴史の狭間に広がる“日本誕生の舞台裏”を、いまあなたの目で確かめてください。